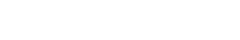| 概 要 |
1.開会挨拶
保健福祉部より挨拶
2.議事
① 令和6年度部会事業活動報告
地域包括支援センター職員より順次説明し、項目ごとに意見交換を実施する。
1)在宅医療看護・介護連携部会 報告 資料P2~
2)認知症施策推進部会 報告 資料P7~
3)介護予防事業 報告 資料P15~
4)生活支援(協議会) 報告 資料P19~
5)地域ケア会議 報告 資料P27~
【医介連携】
- 病院:
Q.市立病院において、退院される方が在宅にスムーズに戻れるため、地域の方や専門職と関わっていること、何らかの手立てを打てばさらに良くなる事柄などないか?
:包括が作成した「退院が決まったあなたへ」というチラシは、本来、病院が退院支援のツールとして作成するような内容で、非常に良いものである。市立病院において、退院される方が在宅にスムーズに戻れるようにするため、介護保険サービスを受けている患者については、担当ケアマネ等の退院後に関わる方とのカンファレンスを開催している。介護サービスを受けていない患者についても、適切な社会資源につながるように、生き生き教室の案内等を活用したり、関係機関との連携を図っていきたい。
- 消防:
Q.救命救急の現状(救急車の台数等)や現状を踏まえ、住民に望みたいことなどあるか?
:宇和島消防は、7台の救急車を所有しているが、昨年度の救急搬送件数は、5463件で過去最高であった。7台全ての救急車が出払うこともあり、私の記憶では初めてである。今年は15.9人に1人が救急搬送されているが、10年前は20.6名に1人 、20数年前は30数名に1人であった。人口が減っているのに救急搬送が増えている。普段からかかりつけ医にかかり、早めに受診したり、普段から検診を積極的に受けて欲しい。夜になると、一人暮らしの方が不安になって、救急車を呼ぶことがある。救急車を呼ぶかの判断に困った場合は、♯7119で相談して欲しい。宇和島市は1日に30件前後相談がある。
【認知症】- 歯科医師:
Q.前回の会議において、愛媛県歯科医師会で、会員を対象とした認知症セミナーを実施されていることを報告あったが、その後どうか?
:愛媛県歯科医師会で、会員を対象とした認知症セミナーを実施している。認知症患者に対応できる歯科医療、口腔ケアを座学として学んだが、形としては上手くはいっていない。認知症患者に対して、専門的な知識を持って対応できる歯科医師の育成を今年度の目標としている。認知症に伴い意思決定が困難で診療を拒否されるケースも多い。施設で口腔トレーニングを行い、摂食嚥下機能を回復から見直すことから始めていただければ。
【地域ケア会議】- ケアマネ:
Q.ケアマネ業務の現状と今後の取組のほか、ケアマネと成年後見人との関りを教えてほしい。
:社会福祉協議会では、高齢者や障がい者の財産管理など、権利擁護を守るため、宇和島地区権利擁護センター(ピット)が市民後見人の養成研修を行っている。令和6年度は基礎・入門、令和7年度は実践編。受講者は23名で、男性が8名、女性が15名。30~70代が受講している。看護、保育、福祉関係者や民生委員 が多い。2年間かけて要請を行った後、意向確認し、市民後見人バンクに登録。養成後もフォローアップ体制を作っていく。ケアマネと後見人の関わりとしては、日頃の状態報告や新たな介護サービスが必要となったり、住まいが変更となった際に、意思決定支援が必要であるため、相談を行っている。成年後見人が行う意思決定支援のプロセスは、普段ケアマネとして目指している根拠ある支援につながる。
【介護予防】- 保険健康課:
Q.市の健康課題であり、要介護状態の原因疾患に起因する高血圧に関し、様々な対策事業について、津島町を重点に実施されていると聞いているが、その事業の効果や評価はどうか?
:市の健康課題であり、要介護状態の原因疾患に起因する高血圧に関し、様々な対策事業について、津島町を重点に実施している。特定健診を分析すると、津島町に高血圧が多い。モデル地区として、重点的に令和5~7年度の期間で行う。ライフステージに沿って、全ての年代に介入する。保育園では、2回目の方が塩分が下がっていたため、意識の改革につながったと評価できる。成人に対して食調査を行ったり、スーパーで減塩食品を調査したり、職域に対して健康教育を行ったり、協定を結んでいる民間会社とイベントを行ったりした。イベントを行ってもなかなか集まりにくいため、既存の団体に健康教育を行い、長いスパンで成果を見ていきたい。やってきたことを全市に広げることが課題。
【地域づくり】- 薬局:
Q.地域住民に対する在宅生活の支援や普及啓発などの活動について教えてほしい。
:出前教室、市民公開講座、イベント等で、骨密度チェックを行っている。2023年においては、ねんりんピックでブースを設け、骨密度、血管年齢チェックを行い、好評であった。今後においても、どんどん行っていきたい。
- 警察:
Q.市民の方が高齢者の安否確認するため、家の中を速やかに確認したいとき、身近な駐在所に相談・対応することは可能か。
:市民の方が高齢者の安否確認するため、家の中を速やかに確認したいとき、身近な駐在所に相談・対応することは可能。2週間に1回、安否確認を行っている。難聴のケースや携帯が故障していたケース、外出しているケース、入院しているケースもあった。中の状況を無制限に確認できるわけではない。家族に連絡し、窓ガラスを割る許可を取ってから行っている。相談前に、郵便受けや直近でいつ見たかを確認して欲しい。独居高齢者で、家族が県外で、家族から包括に電話があった場合、家族の同意を電話でしか確認できないが、事前に承諾を得ているため可能と考えられる。
- いこい:
Q.いこい以外、または、施設関連団体でもよいが、地域の施設や団体が地域住民と関り、認知症や終活など地域づくりに繋がる事業などがあれば教えてほしい。
:おひとりさまの対応に苦慮している。人材不足が弊害となっており、地域における公益的な取り組みとして、防災など、職員の手が常時かからないものが多くなっている。先進的な事例としては、新居浜市。住民と行政が相談し合い、病院との連携や看取り、納骨、供養まで対応しており、居住支援法人の立ち上げも検討している。松山市のある事業所では、認知症の方に対し、1ヶ月間地域の方との訪問を行ってから、介護サービスにつないでいる。すぐにサービスにつなぎ、地域と希薄になってしまうのではなく、当事者に安心感を与え、信頼関係を大切にしてから、フォーマルサービスを導入している。宇和島市には宇和島市の良いところがあるため、一緒に取り組むことができれば。
- 民生委員:
Q.行政等の橋渡し活動のほか、様々な地域づくり活動を実践されている方もおられる。認知症施策など学びの場をつくることができるものか、また、前向きに検討していただく地区があれば教えてほしい。
:近年は、短期で退任する方が多く、そういう機会を設けることが難しい。今年は、一番関心のあった防災の研修を行うが、それだけでは知識を深めるには至らない。そのため、月に1回の会長の定例会で研修を行い、地区に持って帰ることが得策であると考える。配食サービスやまごころ杖等の情報が地域住民に浸透していない。身近な研修よりも高尚な研修が多い。認知症の対応についての基本的なことを講義して欲しい。
- 公民館:
Q.公民館活動の中で、認知症サポートの養成や認知症高齢者への声掛け訓練や、終活などの学びの場をつくることができるものか?
2ヶ月に1度、館長と主事の合同研修会を行っている。防災関係や人権教育に関する研修は行っているが、認知症の研修はまだできていない。今後研修を進めていかなければと思っている。
- 自治会:
Q.自治会の立場からみて、認知症サポートの養成や認知症高齢者への声掛け訓練や終活などの取組への感想など教えてほしい。
:電話や訪問をした際、感謝される方もいる一方で、「ほっといってくれ。静かに暮らしたい。あまり訪ねてくるな。」などと、おっせかいと捉える方もいる。一昨年、明倫公民館で人生会議ノートを作成する機会があったが、参加者に感想を聞くと、死に向かって、深刻な気持ちになってしまう方も多く、好評ではなかった。個人的には、おひとりさまを対象に、準備しておかないとまずいと思っているが、そういう意見もあることを知った。平常時におひとりさまを訪問する支援体制が構築されていない。詐欺を防止するために、電話をわざとに取らない方も多かったりと、複雑な状況である。
- 社協:
Q.地域にある小単位の団体から地域づくりを拡大させるため、協議体事務局としての考えや実際に働きかけができそうな地域や団体があれば教えてほしい。
:関係機関への投げかけ型ではなく、地域住民が主体となるような支援をすることが求められている。地域にある小単位の団体から地域づくりを拡大させるため、協議体事務局として、地域に出向き、住民の関心ごとを丁寧に聞き、活動に活かしていきたい。しがしながら、住民だけでは難しいこともあるため、場所の整備や人とのつながりをサポートしていきたい。初めは、ターゲットを限定せず、広く浅く研修を行い、関心を持った人向けに認知症サポーター養成講座等を行ってみてはどうか。吉田まる等へも働き掛けができるのではないか。働きながら地域貢献をできる機会として、地域支援コーディネーターやボランティアセンターとも共同して、企業向けの出前講座を行っていきたい。
② 協議
事務局より提案事項
各部会、事業の課題を整理したうえでの本会から宇和島市への提言(案)
- 地域の高齢者が望む生き方を実現するため、様々な視点で行う(生きがい、孤立防止 介護・認知症予防、おひとり様支援等)地域づくり活動に寄り添い、支援すること
- 1に掲げる地域づくりのために、属性や世代を問わず、行政・民間・社会福祉法人等多様な主体の交流を通じ、市内外のあらゆる社会資源を適切かつ有効に活用すること
提案事項に異議なし。
➂ まとめ
宇和島保健所:
顔のみえる関係はとても大切。
3.閉会
|